
名古屋・尾張・三河の天然木の注文住宅
Tel 0567-52-1056 9:00-18:00 [日曜/祝日定休]
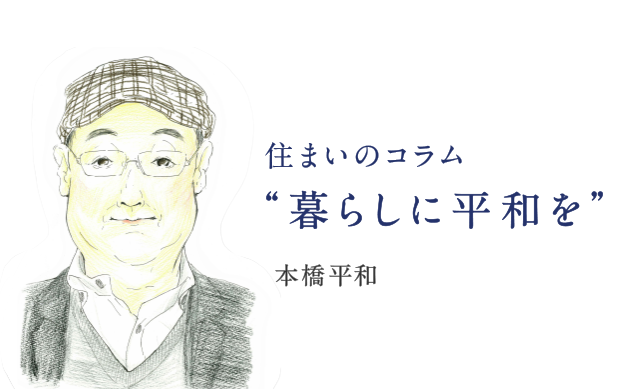
2017.11.24 /
11月20日の月曜日に東白川製材協同組合に行ってまいりました。
今年一番の寒さの中、工場長に工場を案内していただき、また東濃桧のお話をお聞きして大変有意義なお時間を過ごさせていただきました。
渡邊工務店は天然木で建てる本物志向の家をモットーとしています。
天然木を直接買付、自社で検品し、そしてその木材の特質を見極めながら建物のどこで使用するかの番付を行い木材の適材適所を見極めます。
その木材の仕入れ現場を現地現物主義で行って来ました。
 奥の建物が東白川製材協同組合の平屋の事務所です。
奥の建物が東白川製材協同組合の平屋の事務所です。
地場の17の製材業者、素材業者、森林組合の皆様の方々からなる組合で、東白川村の近在は勿論、下呂や中津川エリアの東濃桧を仕入れて製材されている東濃桧ど真ん中の製材協同組合です。
東白川村は人口がおよそ2400人でその70%が木材関係の仕事に従事され、村の面積の90%が森林で、その70%が戦後に造林された森、30%が天然林とお聞きしました。
かつて造林された桧が切り出しの時期を迎えるようです。
東濃桧は厳しい気候の関係で一人前の桧になるまで60年くらいの時間を要するそうで木目が細かく詰まっています。

白いところが夏の年輪で成長も早く太いです。
濃い線が冬の成長年輪で線のように細いですね。
実は同じ桧でも、四国や九州の桧は温暖な気候の為、年輪の太さが倍ぐらいになり東濃桧の半分の30年位で一人前の桧になるそうです。
ちなみに最近伐採した工場内の杉の木の年輪が、温かいエリアの桧の年輪とよく似ているので参考に見せて頂きました。
こんな感じで太いですね。
 和牛なら松坂牛、マグロなら大間のマグロ、桧なら東濃桧というところでしょうか?
和牛なら松坂牛、マグロなら大間のマグロ、桧なら東濃桧というところでしょうか?
また東濃の土壌の特性もあり、東濃桧は香りの元となるフットンチッドも豊富に含まれる為、部屋中にいい香りがします。
愛知県で桧づくりを建てるなら東濃桧ですね。
また、東濃桧品質管理規定が厳格に定められ、適合検査に合格した東濃桧にJASマーク(日本農林規格)が付与されます。
自然に育まれた農産物として扱われています。
ちなみに集成材(エンジニアリングウッド)はJIS規格で認定を受けます。
JIS規格(日本工業規格)は工業標準化法で定められ工業化製品が対象です。
よって、木を見るとか適材適所などという考え方とは遠いところにあると思います。
また製材した材木を機械乾燥するのですが、高温乾燥と中温乾燥の2パターンあるそうです。
中温乾燥は60度~70度で1週間位時間をかけてゆっくり乾燥する方法。
ほぼ天然の状態を保ちます。
高温乾燥は120度位で12時間~20時間かけて乾燥する方法です。
中温乾燥は手間がかかる分、木の性質に天然の趣を残しているので、木材にも生きている証で背割りを入れ、フットンチッドも残っているので桧のいい香りがします。
高温乾燥では少し赤身変化し、香りも無くなっていました。
木材に背割りをすることなく使用でき、ある意味で工業製品のような感じに思えます。
実際の建築現場でも中温乾燥の背割り木材は生きているので胴縁を渡して木自体が呼吸して出来る微妙な収縮に対応します。
高温乾燥材は工業製品のようなので、そのようなひずみもなく直貼りで内装工事をしても不陸や内装材の切れなどの心配はありません。
中温乾燥材は手間が掛かりますが、昔ながらの活きている桧の家として末永く住んで頂けるとお思います。
渡邊工務店の注文住宅の建物はすべて中温乾燥材を使用しています。
但し、一部規格住宅に高温乾燥の桧材を使用しています。
上の段の背割り入りの桧材が中温乾燥材で桧の香りも白い木肌も自然な感じです。
下の段の同じ桧でも赤身のある桧材が高温乾燥材です。

本当に木を知るには山に入り、山の人たちがどんな気持ちで仕事をしているかを知り、実際に現地にきて現物の木を吟味することが大切だと思いますが、最近は難しいこととなったのかなと思います。
直接仕入れている工務店では渡邊工務店が断トツの仕入れ高で、ほとんどの住宅会社ではプレカット業者が卸して、そこで加工された木材を購入されるようです。
4月には渡邊工務店のお客様を対象に、実際の植林の体験や東白川製材組合の工場見学のバスツアーも企画させていただいているので、機会があればぜひご参加ください。

2017.11.14

2017.11.30