
名古屋・尾張・三河の天然木の注文住宅
Tel 0567-52-1056 9:00-18:00 [日曜/祝日定休]
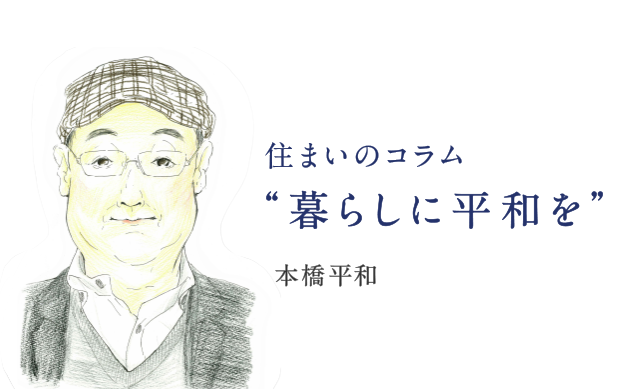
2022.09.08 /
ひと夏の出来事ですが、野鳥のヒヨドリが我が家の庭のハナミズキに巣をつくり、四羽のひな鳥と子育てを終えた親鳥が巣立っていきました。
一度だけ驚かさないようにして、ヒヨドリの巣の写真を撮らせて貰いました。
巣作りの施工力は驚くほど丁寧で、半円状の巣の中にひな鳥が大人しくしていました。
外敵に気づかれず身を守る為なのか、ひな鳥の鳴き声を聴いたことはありませんでした。
綺麗な巣ですが子育てが終わると使うことも無く、翌年の再利用もされないようです。
勿体ないですね。


ヒヨドリがオスとメスのつがいで巣作りをするのは子育ての為です。
ネコやヘビやカラスなどの外敵に見つからないよう2.5m位の高さの木陰にお椀型に巣を作りましたが、その理由は卵やひな鳥の安全を全方位から守るためらしいです。
ところで住まいという言葉は、古くは鳥の巣に由来があるそうです。
古い時代には人間も夫婦で住まいをつくるのは、育児や子育ての為だったと思います。
住まいは巣まいですね。
リスクの高い出産や育児の時に外敵から家族を守るシェルターとしての役割は、ヒヨドリの巣と同じように人の住まいにも必要だったのかなと思います。
昔に比べて人は長生きになり、社会の変化や世帯の意味合いも多様化し、子育て以外にも様々な価値観が家造りに付与されるようになってきました。
ヒヨドリはひと夏の出来事として巣立ちますが、人は社会で生き抜くために長い時間をかけて幼少期から青年期を学びの為に過ごすので、暮らしの本拠となる住まいの環境がその後の人生に大きく影響を与えていくように思います。
立派に振舞う人達やリーダーシップを発揮する人達も、赤ん坊や子どもの時には両親に守られて育ってきた住まいでの暮らしがあったと思います。
幼少期から青年期に家族や人を想う心、そして世界を考える心を育むような住まいで暮らしていれば、大人になってからきっと貴重な経験として人生の財産になるように思います。
時が経過し家具や家屋が古くなった時に、安価で簡単に作られたものは長く使い続けることも修復して直すこともなかなか出来ないように思います。
ただ古いだけではアンティークとしての価値も、心の想いとして記憶に残すことも難しいように思います。
ヒヨドリは何千年の歴史の中で巣作りの技術を遺伝子に伝えてきたと思いますが、人の住まいも確かな材料と、それを活かす技術、そしてその伝承が大切なことと思います。
渡邊工務店の確かな技量と経験で建てられた天然木の家で、家族の歴史を肌で感じ、住まいの空間に心を宿すような愛着が芽生えることによって、成長期に形成される情操(じょそう:美しいものやすぐれたものに触れることで素直に感動することのできる豊かな心。また、その心の働き。)や世界観に少しでも寄与できたなら嬉しく思います。

2022.07.29

2022.09.30