
名古屋・尾張・三河の天然木の注文住宅
Tel 0567-52-1056 9:00-18:00 [日曜/祝日定休]
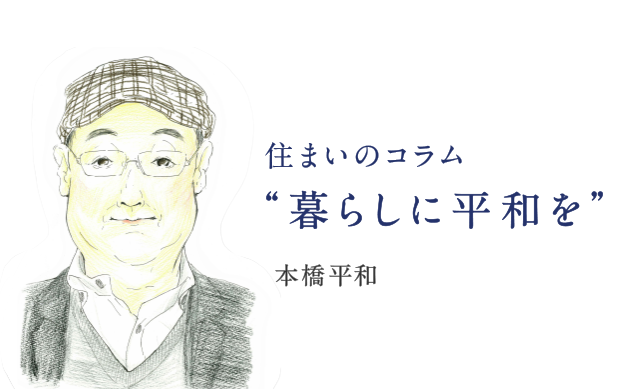
2022.01.17 /
渡邊工務店は今年で創業115周年を迎えることとなりました。
今回は会社の寿命と住宅の長期保証について考えてみたいと思います。
木造建築物の長寿命・耐震性の素晴らしさを説明する時に、1,300年以上前に建築された現存する世界最古の木造建築である法隆寺の話がよく言われますね。
構造体である桧(ひのき)の素材の特質や、地震に強い建築工法、建築に携わった大工の技術がその背景にあると言われています。
しかし、坂本功東京大学名誉教授著「木造建築を見直す」(岩波新書)の中で「法隆寺を建てた大工は、1,300年もつものをつくったのではなく、1,300年もたせるに値する建物をつくったのです。」という文章に少し異なる視点を感じました。
法隆寺の建物が老朽化し、維持管理に必要な補修箇所がでてきても修理と補強を繰り返し、後世に伝えようという先人の想いと、大工の匠の技があってこその1,300年の歴史との考えと理解しました。
歴史的建造物のみならず、身近にあるお寺や神社にもその地域の人々には同じような想いがあると思います。
そのような想いを伝統的な建築会社が家守のように支えていると思います。

渡邊工務店も地域の人々に愛着をもたれ、残される価値のある社寺建築を手掛けさせていただいています。
ご参考リンク:渡邊工務店の社寺建築 施工実績事例
このような家守の話は社寺建築だけでなく個人の住宅建築でも同じではないでしょうか?
そこに住まう家族の想いに寄り添った家を建てて、その後の20年、30年そして60年後の家族の様々なシーンが刻まれた家を、その家を建てた建築会社が家守としてずっと維持管理していくべきだと思います。
そうすると建物の長寿命もさることながら、家守としての建築会社の寿命が建てた家以上に長寿命でないと話になりません。
日本の会社の平均寿命は、一説に30年と言われています。
東京商工リサーチの2018年の調査結果によると建設会社の平均寿命は24年だそうです。
東海エリアでも過去20年位で見ると、愛知県でトップクラスの着工実績のあった上場企業の倒産や、総合住宅展示場に出展していた建築会社が倒産して撤退するケースがありました。
会社の長寿命の為には組織として一定以上の規模が必要だと思いますが、それだけでは不十分のようです。
建築に携わった会社がなくなってしまうのは、その後の建物の維持管理の相談先の問題だけでなく、依頼した建築主の気持ちとしても家族にとっても悲しいことだと思います。
地域密着の建築会社の倒産は、お客様や取引先、地域の皆様、社員やその家族にとってあってはならないことだと思います。
そうならない為には社歴を積み上げ、長寿命の実績を作っていくことがお客様を含めた皆様の安心につながることだと思います。
それには、会社の建築の仕事に対する拘りの姿勢が大切であると考えます。
特に地域密着企業はオーナーの考え方や行動に現れるように思います。
わかりやすい事例では、地域密着建築企業のオーナーは建築現場に足を運び、現地現物で仕事の出来映え確認をすることが当たり前になっていると思います。
私見ですが、建築会社の社長が現場に足を運ばなくなったら不安ですね。
会社が大きくなると飲食やブティックなどの小売業のような異業種に事業を多角化(新しい分野に進出して企業が成長する方法)していく会社もあります。
長期視点で建物工事や経営管理を考える建築業と、日々の売り上げと市況を見ながら細かく管理する業種では経営のスタンスが異なるように思います。
本業から外れていくことは、経営者が建築現場に足を運ばなくなる要因にもなるかも知れません。
渡邊工務店は60年長期保証システムを運用しています。
システムとしての60年という期間を担保するために、115年の社歴のおよそ半分を期間設定していますが、家守としての役割は建築に携わった建物がある限りずっとお付き合いしていく所存です。
時代の要請に従い、お客様と建築会社の家守として、末長いお付き合いのお約束を交わす為、具体的な内容を文書化し明示したのが60年長期保証システムです。
ご参考リンク:60年長期保証システム概要
![]()

60年長期保証システムは新築の建物のお引渡しから始まります。
長期にわたる保守管理の設定期間を社歴以上の期間で組み立てることは書類上可能でも、企業として本当に信義誠実にお約束できるのか不安です。
115年存在している渡邊工務店だからこそ「百年住み継ぐ家」を建て、60年の長期保証をお約束することができます。
渡邊工務店はこれからも社歴を積み上げて、60年長期保証システムの運用への信頼を高め、お客様の家守として末長くお付き合いしていくことへの期待にお応えしていく所存です。

2021.12.13

2022.02.18