
名古屋・尾張・三河の天然木の注文住宅
Tel 0567-52-1056 9:00-18:00 [日曜/祝日定休]
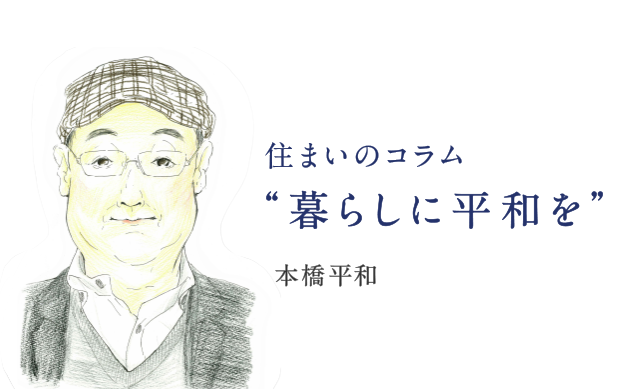
2021.06.17 /
先日、ある番組を見ていると、欧米の方が日本家屋の照明は昼光色(ちゅうこうしょく:他の色と比べて白っぽく青みがかった最も明るい色)のLEDや蛍光灯を多用していて、夜でも昼間のように明るく白すぎて落ち着かないと仰っていました。
このようなご指摘はライティングデザインとして、日本の中でも多くの方からご指摘されるところになっています。
そういえば欧米の家屋のリビングや寝室は電球色のLEDや電球を薄暗く配したり、キャンドルや暖炉の火を使ったりして暖色の薄明な空間をつくるケースが多いと思います。
天井シーリングライトがなく、灯りはスタンドで設えられている客室のホテルはよく目にします。
同じようにホテルのラウンジバーやレストランも照明は落ち着いた感じです。
恐らく、折角の夜を昼間のように明るくしないで、豊かな大人の夜の時間を過ごしてほしいとのことだと思います。
海外の映画やテレビの海外旅行記でみるナイトライフを垣間見ると羨ましくもあります。
ところで昭和初期に文豪の谷崎潤一郎が「陰翳礼賛」(いんえいらいさん)という随筆で、こちらの欧米の方と同様なことを仰っています。
近代化して電灯などで明るくなり、便利な電化製品が日常の暮らしに取り入れられる中、室内の設えや日本古来のライティングに対する想いを語ってらっしゃいます。
近代化と共に欧米に憧れ影響を受けてきた日本の新築住宅は、現在でも可能な限り部屋の隅々まで明るくして、陰翳(いんえい:光の当たらない暗い部分)を消す事に執着する傾向が少し残っているように思いますが、それ以前の日本ではむしろ陰翳を認めるところに、日本古来の美意識・美学の特徴があると主張されているように思います。
こうした主張のもと、建築、照明、紙、食器、食べ物、化粧、能や衣装の色彩など、多岐にわたって陰翳の考察がなされていて、海外でも翻訳されていてデザイン論としても評価が高いようです。
欧米の方も谷崎潤一郎も日本や海外のライティングに対して、相手方を真逆な立場として捉えて同様なことを言っているようで不思議な感じです。
陰翳礼賛の例えとして、白塗りの舞妓さんは白昼や蛍光灯の下では違和感がありますが、夜の和室で行燈(あんどん: ろうそくや油脂を燃料とした炎を光源とする照明器具)の揺らめく灯りに照らされた姿は妖艶そのものです。
同じように、金屏風や螺鈿(らでん:夜光貝その他の貝類を彫刻して漆地や木地などにはめこむ技法)細工、金蒔絵(きんまきえ:漆器の表面に金箔を細かくした消粉で絵や文様、文字などを描き、器面に定着させたもの)や真っ赤な漆器も、蛍光灯の下や昼間にそれだけを見ると少し悪趣味かなと思うところもありますが、老舗旅館や料亭でそれなりの薄明のライティングと設えで見ると、違和感なく艶めかしく受け入れられます。
家の内装やインテリア、照明を考える時に、大壁工法で白い壁クロスを張り、明るいライティングにすることも良いとは思いますが、成熟化した世の中になり、家で過ごす時間を大切にする事も多くなってくると思うと、陰翳礼讃に習う事も考えてみてはどうでしょうか。
渡邊工務店は本格木造軸組工法を基本としていて、柱だけでなく内装に杉や桧の天然木の素材を活かす工夫もしています。
暖色系のライティングとの相性が良く、生成色(きなりいろ:ごく淡い灰色がかった黄褐色)の壁材と共に和室の障子や畳では、ライティングの映しだけでなく、トワイライトの日が差し込む障子紙ともマッチすると思います。
量産型の工業化住宅やプレハブ工法だとなかなか困難だと思いますが、日々の暮らしに日本人が古くから持っていた趣味や美意識を取り入れてみるのも良いのかなと思います。
■施工実績について詳しくはこちら

2021.06.03

2021.06.29