
名古屋・尾張・三河の天然木の注文住宅
Tel 0567-52-1056 9:00-18:00 [日曜/祝日定休]
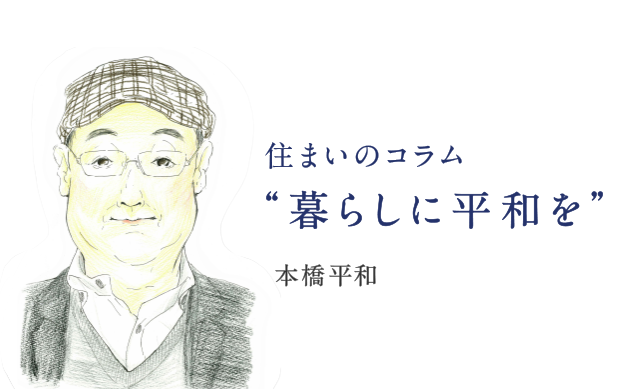
2018.04.02 /
方位をかなり気にされるお客様がいらして、今住んでいるアパートから辰巳の方向でないといけないのですが、ぴったりの土地が方位から外れているのでどうしたらいいかなとのご質問を受けました。
このこと以外にも家相や、特に鬼門について同じように相談されることがありましたので少しまとめてみました。
古来、中国にしても日本にしても国を治める最重要課題は、戦争・農業・治水でした。
対策は、気候・自然、地理を良く知り、他国やライバルに先んじて対策を講じること。
よって、時の皇帝や、王などの権力者の直近にはかならず気候・自然、地理を良く知るものを置きました。
日本では陰陽師の阿部晴明が有名です。
かつて映画で公開されていた「レッドクリフ」三国志の赤壁の戦いですが、ここに出てくる有名な諸葛孔明も同様です。
赤壁の戦いでは20万の曹操軍に対し劉備・孫権軍5万が諸葛孔明の火計で大勝しました。
圧倒的な水軍兵力をベースに、船と船をつなぎ合わせて水上の要塞を形成した曹操軍の唯一の警戒は、火責めによる木造船の炎上でしたが、その時期は曹操軍が風上で、風下になる東風の風は吹かないはずでした。
しかし諸葛孔明は、ある条件が微妙に重なると東風の風が吹く事を地元の農民より知りえていたので、毎日東風の風が吹く呪術の儀式を行い、その気象条件が重なった時、火責めに出たのです。
周りの人達は天を操る超能力者に見えたと思います。
しかし、諸葛孔明には予め分かっていた事だったのですね。
当時の庶民の常識では解明できない事を鬼や妖怪の仕業とし、それらの事に対し当時の科学技術を駆使した対応策が方位でした。
その技術は権力者の側近の陰陽師や呪術者や宗教家や学者の固有のものであったので、周りのものから見れば神秘的であったと思います。
次第に庶民の生活の中にその神秘的な様式が引用され、習俗として定着していきました。
習わしや儀式として定着してしまったところが、現代の科学の時代でも方位や家相や鬼門にこだわる人達が大勢いることとなった要因だと思います。
数々の難問を解決する阿部晴明や諸葛孔明のやっているようなことを、同じように庶民でも取り組めば、自分の問題も解決し、そのよりどころの方位学や家相・気学・占星術・風水を信奉してしまう事は無理からぬ事です。
但し、元々国政レベルの国の存亡をかけた技術と、普段の生活ではあまりにも次元が異なるので、普段の日常の生活レベルでは不便を感じますね。
そんなところから、平安時代では「方位違え」といって目的地方位が凶方になるなら、まず別のところにいって目的地を吉方にしてから移動したり、方位違神社(大阪の堺市にある由緒ある神社)にお参りして吉方にするように工夫していました。
私達も庶民のレベルでは戦争するわけでもないし、鬼門の方位から敵が攻めてくるわけでもないので、暮らし易い土地や間取りを優先し、儀式や習俗として気になるところは先人に習って「方位違え」や方位違神社で御祓いをして安心する方が、合理的であると思います。
このあたりは平安時代の古人の生活習慣に見習っても良いのではないでしょうか。
【鬼門の起源】
鬼門という言葉はよく耳にします。
鬼門という文字だけ見れば鬼の門、鬼の出入りする門、というイメージです。
家相は、中国の陰陽五行説から生まれ、日本に伝わり、日本の陰陽道の中で家相学として発展をとげました。
何故、北東方位が鬼門なのか。
調べてみれば諸説有りますが、一番有力な説が匈奴説でしょう。
匈奴とは、紀元前3〜5世紀のころ今のモンゴル高原の地域で栄えた騎馬民族です。
この民族は騎馬戦術(当時の戦争のハイテク技術)にすぐれ、とにかく強い。
とても当時の中国人の敵では無かったのです。
時の中国皇帝であった秦の始皇帝はこの民族をとても恐れ、鬼門方位に万里の長城の建設にとりかかったほどです。
この民族が北東(鬼門)の方角から強弓を駆使して、騎馬で疾風のごとく攻めてきたのです。それは鬼と恐れる気持ちも解ります。
そんな敵が攻めてくる方角に玄関を作るわけにはいきませんね。
日本の家相でもこの北東の鬼門方角は忌み嫌います。
そうして日本に伝来した忌み嫌われる鬼門ですが、奈良時代に時の朝廷が吉凶を判断する際に用いられ始めた風水は、朝廷を起点として北東と南西に細長く伸びる日本列島の形状と、中国から伝来した鬼門の戒めと合致し、重用され始めました。
日本では何故「鬼門、裏鬼門」が風水の中でも特に重きを置かれるのか、それは大和朝廷が起こって700年間の列島制圧の歴史、戦いの歴史がまさに北東(鬼門)の夷狄と南西(裏鬼門)の夷狄を熊襲や土蜘蛛と称して恐れ戦った過去の歴史が、鬼門の思想とマッチしたからだという考え方もあります。

2018.03.15

2018.04.11